
講師紹介
2025年度東京第1期 講師紹介
本講座は、研究者、アーティスト、起業家といった多彩な講師陣をラインナップしています。

蓮行 (れんぎょう)
京都大学経営管理大学院特定准教授、劇作家、演出家、俳優、劇団衛星代表
専門は演劇教育、コミュニケーションデザイン。「小劇場での演劇でしか絶対に表現できない舞台表現」を極めるべく、1995年に劇団衛星を設立。京都を拠点に、既存のホールのみならず、寺社仏閣・教会・廃工場等「劇場ではない場所」で公演を数多く行い、茶道劇「珠光の庵」や裁判劇「大陪審」などの代表作を全国で上演する。同時に、演劇の持つ社会教育力に着目し、そのポテンシャルを利用したワークショップ事業を多く手がける。並行して研究活動に取り組み「演劇のないところに演劇を送り込む」活動を幅広く展開している。
[著書]
蓮行,平田オリザ「演劇コミュニケーション学」日本文教出版,2016年
平田オリザ,蓮行「コミュニケーション力を引き出す:演劇ワークショップのすすめ」PHP新書,2009年
谷口忠大,石川竜一郎,中川智皓,蓮行,井之上直也,末長英里子,益井博史 (担当:分担執筆, 範囲:第4章 演劇ワークショップ──ロールプレイの空間を創る)「コミュニケーション場のメカニズムデザイン」 慶應義塾大学出版会, 2021年

淺野 和人(あさの かずと)
大田ゲートウェイ㈱ 代表取締役
1998年 京都大学工学部材料工学科卒
大学卒業後、ベンチャー企業を経て、VCに転職。製造業に特化した投資を行う専門ファンドにて投資とコンサルティングに従事。2009年に独立し、現在に至る。
「ものづくりの国」の再興を目指し、かつての繁栄を支えた中小製造業の経営支援を行うなか、個社ごとの対策では限界があると感じ、複数企業の連携による新製品開発プロジェクト(脱下請、メーカー化)を推進中。
農漁業用機械、建設現場の作業支援ロボット等、高齢化や人手不足が深刻化する産業分野の課題解決に、町工場の技術の結集によるソリューションで挑む。

飯塚 隼光 (いいづか たかみつ)
日本大学経済学部 専任講師
一橋大学大学院,経営管理研究科博士後期課程修了。2021年から京都大学経営管理大学院管理会計寄附講座特定助教として勤務。2025年度から現職。専門は管理会計。優れた品質の製品を製造する企業に対するインタビュー調査・研究を実施。その過程で,優れた製品を生み出しつづける企業において複雑な管理会計が用いられているわけではなく,非常に「シンプル」な管理会計が実施されていることが判明。以降こうした実務をシンプル管理会計として研究を続けている。
[論文]
飯塚隼光・古井健太郎. 2022.「中小製造企業におけるシンプルな管理会計実践―管理会計の不在研究を手掛かりにして―」『原価計算研究』46(2): 40-52.
[ケース教材]
飯塚隼光・越智崇実史「株式会社レインボークリーンの事例」
飯塚隼光・鈴木克欣・澤邉紀生「会計数値による現場支配からの脱却」

石山恭子(いしやま きょうこ)
NPO法人子育て支援グループamigo理事長
大学でコミュニケーション学を学び、日系航空会社に勤務。
出産を機に「子育て支援グループamigo」に出会い、産前産後・子育て支援の重要性を実感し、子連れボランティアとして参加。
「産前産後のセルフケア講座」を企画・開発し、世田谷区を中心に展開(2006年〜)。
現在、36名のスタッフと共に行政等と連携しながら、世田谷区内2ヶ所の地域子育て支援拠点の運営や利用者支援事業(基本型)に従事している。
年間のべ約3,000組の親子と関わりながら、母親の心身の健康サポートや仲間づくりを推進。
2023年には、老若男女ウェルビーイングがこだまする場を目指し「小さなカルチャーセンターpublicoパブリコ」を開設。実践知を活かしたコミュニティデザインに取り組んでいる。
公益信託世田谷まちづくりファンド運営委員(2025年〜)。スポーツウエルネス学修士。

小野敬済(おの たかずみ)
東京大学 大学院情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻 特任研究員
「誰もが自分らしく暮らせる社会」をめざして、主観的Well-being、社会的包摂、外出を研究。
バックグラウンドは理学療法学で、要支援・要介護高齢者の外出行動の研究からキャリアをスタートした。
近年は、主観的Well-beingや社会的包摂の研究に従事、理論的には社会学や社会福祉学、手法的には計量心理学的手法、疫学的手法、質的研究法等を使って研究活動を行っている。
また、青山学院大学ワークショップデザイナー育成プログラムでワークショップデザイン(WSD)を学び、研究や実践の中でWSDを実践している。
最近は、包摂性指標の開発と実証研究やインクルーシブ保育の推進に向けた情報・教育的コンテンツの整備事業等に取り組んでいる。

絹川友梨(きぬがわ ゆり)
インプロ・ワークス(株)代表取締役、俳優、演出家、翻訳家、ワークショップファシリテーター
専門は即興演劇(インプロ)、演劇教育、認知科学。台本のない演劇(=インプロ)の面白さや深さを伝えるために、1994年にインプロ・ワークスを設立。東京を拠点に、子どもからシニアまで、出張授業や演劇ワークショップから企業研修まで、さまざまな対象年齢や目的に沿って、演劇やインプロを用いたワークショップを国内・海外で展開している。並行して、演劇の即興性や創造性に関して、認知科学的手法で研究を行っている。
.jpg)
佐野 未来(さの みく)
ビッグイシュー日本東京事務所所長
大阪生まれ。高校卒業後渡米し、ウェスタン・ミシガン大学で英文科・ジャーナリズムを専攻。卒業後帰国し、英語講師、翻訳・通訳などを経験。2002年に「質の高い雑誌を発行し、ホームレ状態にある人の独占販売とすることで、すぐにできる仕事をつくる」というビッグイシューUKの仕組みに出会い、日本一路上生活者の多かった大阪での創刊を仲間とともに検討。2003年にビッグイシュー日本を3人で創業。2007年まで雑誌『ビッグイシュー日本版』編集部で副編集長・国際担当。2008年から東京事務所に移動し、社会的排除・孤立の最たる状態であるホームレス問題から、孤立せずに生きられる社会を考えるため、様々なセクターの人たちとの協働を進めている。
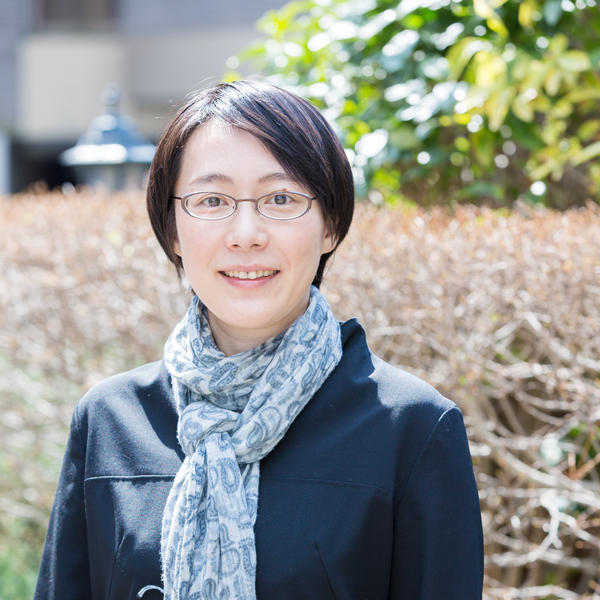
二瓶美里(にへい みさと)
東京大学 大学院情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻 教授
多様性包摂共創センター/高齢社会総合研究機構
博士(工学)。国立障害者リハビリテーションセンター研究所等を経て現職。専門は、生活システム、人間・生活支援工学、アクセシブルデザイン。真に人に有用な機器を提供するために、工学の枠組みを超えて、生活や人生そのもの、人と支援機器の関わりを様々な観点から紐解き、人や社会に役立つ生活システムを提案することを目指している。
[論文]
二瓶美里, 第11章 健康長寿を支えるテクノロジー, 「高齢者および高齢社会に関する検討ワーキンググループ」報告書, 日本老年学会, 2024.
二瓶美里, 他, 障害者の支援機器開発におけるモニター評価のためのガイドブック, 2023.

丸本 瑞葉 (まるもと みずは)
株式会社SciEmo 代表取締役 / CEO
関西大学商学部卒、京都大学経営管理大学院修了。メーカーにてITソリューションの企画開発やM&Aなどの事業開発に従事。京都大学で新規事業創出方法論を専門に研究し、感情を重視した新規事業創出方法論を開発する。MBA取得後、株式会社SciEmoを設立。新規事業創出サポート、ブランディング、新規事業ワークショップをサービス提供しながら、自社でもクローズドSNSサービスやITソリューション・プロダクトを新規開発・販売している。

村瀬健(むらせ けん)
フジテレビ ドラマ制作部 統括チーフプロデューサー
1973年生まれ、愛知県出身。早稲田大学社会科学部を1997年に卒業し、日本テレビに入社。ドラマプロデューサーとして『終戦60年ドラマ・火垂るの墓』『14才の母』などの話題作を手掛けた後、フジテレビに転職。テレビドラマとして『太陽と海の教室』『BOSS』『信長協奏曲』『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』『いちばんすきな花』、映画でも『信長協奏曲』『帝一の國』『約束のネバーランド』『キャラクター』などのヒット作を送り出す。2022年に手掛けたドラマ『silent』が大ヒットを記録。社会現象と呼ばれるほどのムーブメントを起こす。昨年7月『silent』チームで制作した『海のはじまり』が大ヒット。「MIPCOM BUYERS‘ AWARD for Japanese Drama グランプリ」「TVerアワード2024ドラマグランプリ」など数々の賞を受賞。

吉田 絵理子 (よしだ えりこ)
川崎医療生活協同組合 川崎協同病院 総合診療科 科長
一般社団法人にじいろドクターズ 理事、東京慈恵会医科大学 臨床疫学研究部 訪問研究員
全日本民主医療機関連合会 人権と倫理センター SOGIEコミュニティ
2018年にバイセクシュルかつXジェンダーであることを公表し、LGBTQ当事者医師としての活動を開始した。2021年にはプライマリ・ケアに従事する医師5名で一般社団法人にじいろドクターズを設立し、理事として主に医療関係者を対象にLGBTQの人々のケアに関する講演活動やワークショップ等を行っている。日本プライマリ・ケア連合学会DE&I推進委員会、日本医学教育学会EDI推進委員会の委員を務め、自身の医療機関が所属する全日本民医連では新たにSOGIEコミュニティを創設し、全国どこででも、どんなセクシュアリティの人でも安心して医療にアクセスできるよう啓発を進めている。
[著書]
2022年刊行 南山堂 『医療者のためのLGBTQ講座』 吉田絵理子総編集
2024年刊行 日本看護協会出版会『LGBTQ+医療現場での実践Q&A』武田裕子・吉田絵理子・宮田瑠珂編著

渡辺 貴裕 (わたなべ たかひろ)
東京学芸大学教職大学院准教授
専門は教育方法学、教師教育学。京都大学大学院教育学研究科博士後期課程満期退学。演劇的手法を用いた学習の可能性を現場の教員と共に探究する「学びの空間研究会」を主宰。演劇教育・ドラマ教育関連の業績に関して、日本演劇教育連盟より演劇教育賞、全国大学国語教育学会より優秀論文賞、日本教育方法学会より研究奨励賞を受賞。授業や模擬授業の「対話型検討会」の取り組みなど教師教育分野でも活躍。
著書として『なってみる学び ―演劇的手法で変わる授業と学校』(共著、時事通信出版局)、『小学校の模擬授業とリフレクションで学ぶ 授業づくりの考え方』(単著、くろしお出版)、『流行に踊る日本の教育』(共著、東洋館出版社)、『〈教師〉になる劇場』(共著、フィルムアート社)など。
2025年度東京講座スケジュールはこちら
2024年度京都第1期 講師紹介

蓮行 (れんぎょう)
京都大学経営管理大学院特定准教授、劇作家、演出家、俳優、劇団衛星代表
専門は演劇教育、コミュニケーションデザイン。「小劇場での演劇でしか絶対に表現できない舞台表現」を極めるべく、1995年に劇団衛星を設立。京都を拠点に、既存のホールのみならず、寺社仏閣・教会・廃工場等「劇場ではない場所」で公演を数多く行い、茶道劇「珠光の庵」や裁判劇「大陪審」などの代表作を全国で上演する。同時に、演劇の持つ社会教育力に着目し、そのポテンシャルを利用したワークショップ事業を多く手がける。並行して研究活動に取り組み「演劇のないところに演劇を送り込む」活動を幅広く展開している。
[著書]
蓮行,平田オリザ「演劇コミュニケーション学」日本文教出版,2016年
平田オリザ,蓮行「コミュニケーション力を引き出す:演劇ワークショップのすすめ」PHP新書,2009年
谷口忠大,石川竜一郎,中川智皓,蓮行,井之上直也,末長英里子,益井博史 (担当:分担執筆, 範囲:第4章 演劇ワークショップ──ロールプレイの空間を創る)「コミュニケーション場のメカニズムデザイン」 慶應義塾大学出版会, 2021年

あごうさとし
劇作家・演出家・THEATRE E9 KYOTO芸術監督
「演劇の複製性」「純粋言語」を主題に、有人・無人の演劇作品を制作する。
2014年9月-2017年8月アトリエ劇研ディレクター。2018年、美術家森村泰昌の一人芝居を演出し、ポンピドゥーセンターメス(仏)、ジャパンソサイエティ(米)にて上演。
2017年1月、(一社)アーツシード京都を大蔵狂言方茂山あきら、美術作家やなぎみわらと立ち上げ、2019年6月にTHEATRE E9 KYOTOを設立・運営する。
2021年上演のオペラ「ロミオがジュリエット」(太田真紀&山田岳主宰 作曲:足立智美)を演出し令和3年度文化庁芸術祭賞大賞とサントリー芸術財団第21回佐治敬三賞の両賞を受賞。

飯塚 隼光 (いいづか たかみつ)
京都大学経営管理大学院管理会計寄附講座特定助教
一橋大学大学院,経営管理研究科博士後期課程修了。2021年から京都大学経営管理大学院管理会計寄附講座特定助教として勤務。2024年から現職。専門は管理会計。優れた品質の製品を製造する企業に対するインタビュー調査・研究を実施。その過程で,優れた製品を生み出しつづける企業において複雑な管理会計が用いられているわけではなく,非常に「シンプル」な管理会計が実施されていることが判明。以降こうした実務をシンプル管理会計として研究を続けている。
[論文]
飯塚隼光・古井健太郎. 2022.「中小製造企業におけるシンプルな管理会計実践―管理会計の不在研究を手掛かりにして―」『原価計算研究』46(2): 40-52.
[ケース教材]
飯塚隼光・越智崇実史「株式会社レインボークリーンの事例」
飯塚隼光・鈴木克欣・澤邉紀生「会計数値による現場支配からの脱却」
-1024x683.jpeg)
上田假奈代(うえだ・かなよ)
詩人
1969年・吉野生まれ。3歳より詩作、17歳から朗読をはじめ、18歳から京大西部講堂に出入りし、今から思えばアーツマネジメントを学ぶ。「下心プロジェクト」を立ち上げ、ワークショップなどの企画、場作りを開始。2001年「詩業家宣言・ことばを人生の味方に」と活動する。
2003年、大阪・新世界で喫茶店のふりをしたアートNPO「ココルーム」を立ち上げ、2012年に開講した「釜ヶ崎芸術大学」はヨコハマトリエンナーレ2014に参加。
2016年ゲストハウス開設。釜ヶ崎のおじさんたちとの井戸掘りなど、あの手この手で地域との協働をはかる。
大阪公立大学都市科学・防災研究センター研究員、NPO法人こえとことばとこころの部屋(ココルーム)代表理事。堺アーツカウンシル プログラム・ディレクター。大手前大学非常勤。著書「釜ヶ崎で表現の場をつくる喫茶店、ココルーム)フィルムアート社

宇野 明香 (うの さやか)
NPO法人happiness、京都市里親会 理事
2016年より京都市南区にてハピネス子ども食堂を立ち上げる。以来年間延べ利用者数は5500名に登る。2019年からはコミュニティカフェをオープン。地域のシニアクラブと協働し高齢者の居場所づくりにも取り組み、またひきこもり状態にある人々の就労支援の受け入れも実施。2022年には女性用シェルターを民間の資金を活用しスタート。同年、子ども食堂の認知度向上を目指したイベント「西寺公園秋祭り」を開催。地域、企業、行政を巻き込み、子育て世帯をはじめとした約3000人を超える来場者を記録。
IMG_3322-1024x768.jpg)
谷 亮治 (たに りょうじ)
京都市役所 地域自治推進室 まちづくりアドバイザー、大学講師
1980年大阪生まれ。博士(社会学)。専門社会調査士。京都市まちづくりアドバイザーのほか、劇団「ぬるり組合」作家、演出家。谷町町内会会長。
大学在学中より、住民参加のまちづくりの実践と研究に携わる。大学院で研究を続ける傍ら、2006年よりまちづくりNPO法人の事務局として京都市の公共施設の委託運営の現場で実務経験を積む。2011年より現職。
代表作に『モテるまちづくり−まちづくりに疲れた人へ。』(まち飯叢書、2014)。2014年から、各地の本書に関心を持つ方と語り合う読書会「モテまち読書会」ツアーを実施。2017年4月時点で55箇所延べおよそ1500名の実践者と語り合ってきた。その読書会ツアーで得られたフィードバックを元に、『純粋でポップな限界のまちづくり−モテるまちづくり2』(まち飯叢書、2017)を出版。近著に『世界で一番親切なまちとあなたの参考文献』(まち飯叢書、2020)がある。

谷口 忠大 (たにぐち ただひろ)
京都大学大学院情報学研究科教授、一般社団法人ビブリオバトル協会代表
2006年京都大学工学研究科博士課程修了。博士(工学・京都大学)。2005年より日本学術振興会特別研究員(DC2)、2006年より同(PD)。2008年より立命館大学情報理工学部助教、2010年より同准教授。2015年より2016年までImperial College London客員准教授。
2017年より立命館大学情報理工学部教授。2024年より現職。知的書評合戦ビブリオバトル発案者。コミュニケーション場のメカニズムデザインの理論を構築。記号創発ロボティクスを核としたAI・ロボティクスの研究者。広く「人を系に含んだ創発システム」が対象。
[著書]
谷口忠大「賀茂川コミュニケーション塾ービブリオバトルから人工知能まで」世界思想社(2019)
谷口忠大「イラストで学ぶ 人工知能概論 改訂第2版」講談社(2020)
谷口忠大、石川竜一郎ほか「コミュニケーション場のメカニズムデザイン」 慶應義塾大学出版会 (2021)
谷口忠大「ビブリオバトル 本を知り人を知る書評ゲーム」文藝春秋(2013)
他多数

中脇 健児(なかわき けんじ)
大阪芸術大学 准教授、京都精華大学・京都芸術大学 非常勤講師
堺アーツカウンシルプログラムオフィサー、伊丹市文化振興ビジョン策定委員会 会長
各地で市民協働のプロジェクトやコミュニティプログラムを手がけ、劇場・ミュージアム・図書館・公園・商店街・団地などを多様な人たちが出会い・創造していく場に変えている。またファシリテーターやアートプロデューサーの育成も手掛ける。兵庫県伊丹市で手がけた「伊丹オトラク」「鳴く虫と郷町」は地域連携・地域協働のプロジェクトとして20年続く。(「鳴く虫と郷町」は2015年「第6回地域再生大賞」優秀賞受賞)
2021年に京都市立芸術大学院にて、関係や場を扱う美術家、小山田徹氏に師事し、改めて自身の活動を見直す。現在はコミュニティ活動を推進する際に発生する「結束の強さ」の逃れ方を模索し、「社会の出合頭を変えるお手伝い」「弱い場の考察」「ふりの研究」をテーマに活動する。釜ヶ崎芸術大学(旧ココルーム)にて、月2回程度、まかないキッチンスタッフのふりをしている。
[共著]
『タウンマネージャー』『地域×クリエイティブ×仕事~淡路島発ローカルをデザインする~』(ともに学芸出版)

平田 知之(ひらた ともゆき)
芸術文化観光専門職大学専任講師
東京都立高校で11年、国立中高一貫校で25年国語科教師や古文教師をつとめた。成り行きで2004年から演劇の専門家と組んだ授業開発を開始。文科省「コミュニケーション教育会議」WG委員、東京学芸大学非常勤講師を経て、2021年芸術文化観光専門職大学の新設を機に今さらのように研究の場に赴任。演劇教育史、演劇ワークショップを専門に、但馬(兵庫県北部)地域の豊富な演劇ワークショップ現場で年間150日強のフィールドワークを行い、「学校」という現場の多様性や魅力を再発見しつづけている。大学以外に、看護専門学校や総合高校、中学校などでも演劇をつかった授業を継続的に行っている。
[著書]
佐藤信編『学校という劇場から-演劇教育とワークショップ』論創社 第6章「演劇人と教師は協働できるのか」を分担執筆

丸本 瑞葉 (まるもと みずは)
株式会社SciEmo 代表取締役 / CEO
関西大学商学部卒、京都大学経営管理大学院修了。メーカーにてITソリューションの企画開発やM&Aなどの事業開発に従事。京都大学で新規事業創出方法論を専門に研究し、感情を重視した新規事業創出方法論を開発する。MBA取得後、株式会社SciEmoを設立。新規事業創出サポート、ブランディング、新規事業ワークショップをサービス提供しながら、自社でもクローズドSNSサービスやITソリューション・プロダクトを新規開発・販売している。

吉田 絵理子 (よしだ えりこ)
川崎医療生活協同組合 川崎協同病院 総合診療科 科長
一般社団法人にじいろドクターズ 理事、東京慈恵会医科大学 臨床疫学研究部 訪問研究員
全日本民主医療機関連合会 人権と倫理センター SOGIEコミュニティ
2018年にバイセクシュルかつXジェンダーであることを公表し、LGBTQ当事者医師としての活動を開始した。2021年にはプライマリ・ケアに従事する医師5名で一般社団法人にじいろドクターズを設立し、理事として主に医療関係者を対象にLGBTQの人々のケアに関する講演活動やワークショップ等を行っている。日本プライマリ・ケア連合学会ダイバシティ推進委員会、日本医学教育学会多様性推進委員会の委員を務め、自身の医療機関が所属する全日本民医連では新たにSOGIEコミュニティを創設し、全国どこででも、どんなセクシュアリティの人でも安心して医療にアクセスできるよう啓発を進めている。
[著書]
2022年4月刊行 南山堂 『医療者のためのLGBTQ講座』 吉田絵理子総編集
2023年4月発行 全日本民主医療機関連合会『にじのかけはし』吉田絵理子著
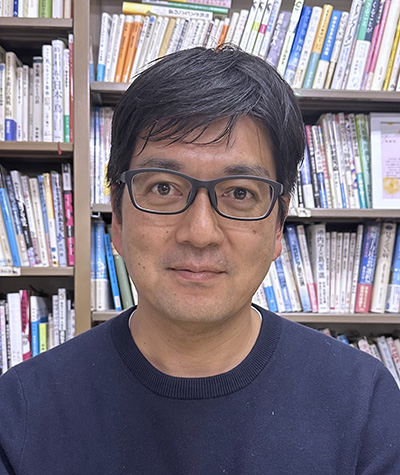
吉田 耕一 (よしだ こういち)
有限会社ビッグイシュー日本 大阪事務所長・販売担当
1979年大阪府高槻市生まれ。関西学院大学文学部卒業。大学卒業後、インド・コルカタ(カルカッタ)にあるマザーテレサの施設でボランティア活動を行う。ボランティアで様々な刺激を受け、帰国後、たまたま大阪の路上で見かけたビッグイシュー販売者のことを友人から教えてもらい、ビジネスの手法で社会問題の解決に挑戦する社会的企業に興味を持つ。その後、ビッグイシューのボランティアを経て、2005年より販売サポートスタッフとして就職。社会的排除・孤立の最たる状態であるホームレス問題からみんなが活き活きできる社会を考えながら販売者の日々のサポート、イベント企画、講演活動などを行う。現在は大阪事務所長を兼務し、事務所運営などを行う。

渡辺 貴裕 (わたなべ たかひろ)
東京学芸大学教職大学院准教授
専門は教育方法学、教師教育学。京都大学大学院教育学研究科博士後期課程満期退学。演劇的手法を用いた学習の可能性を現場の教員と共に探究する「学びの空間研究会」を主宰。演劇教育・ドラマ教育関連の業績に関して、日本演劇教育連盟より演劇教育賞、全国大学国語教育学会より優秀論文賞、日本教育方法学会より研究奨励賞を受賞。授業や模擬授業の「対話型検討会」の取り組みなど教師教育分野でも活躍。
著書として『なってみる学び ―演劇的手法で変わる授業と学校』(共著、時事通信出版局)、『小学校の模擬授業とリフレクションで学ぶ 授業づくりの考え方』(単著、くろしお出版)、『流行に踊る日本の教育』(共著、東洋館出版社)、『〈教師〉になる劇場』(共著、フィルムアート社)など。
