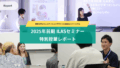2025年6月13日(金)に、京都大学百周年時計台記念館 国際交流ホールにて、「京都大学コミュニケーションデザインとDE&Iコンソーシアム シンポジウム2025」が開催されました。
このシンポジウムは、社会や組織におけるDE&I(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)の実践や課題を共有し、参加者同士の対話を通じて“集合知”を育むことを目的として開催されたものです。
本レポートでは、第1部の基調トークセッション、および第2部のポスターセッション・ポスターミーティングについてご紹介します。
第1部
開会にあたり、コンソーシアム共同代表である蓮行先生(京都大学経営管理大学院特定准教授)より、本シンポジウムの趣旨説明がありました。

京都大学DE&Iコンソーシアムは、大学単体では解決が難しい社会課題に対し、企業やNPOなど多様なセクターと連携しながら、ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン(DE&I)を推進するための社会連携の基盤として設立されました。蓮行先生は、DE&Iの理解には「公正性(Equity)」の視点が欠かせないと述べた上で、「ひとりひとりが頑張っていくのは大事。けれど、個人の努力だけでなく、環境・制度・文化を包括的にデザインしようとする『コミュニケーションデザイン』の考え方が重要」だと強調しました。

基調トークセッション
テーマ:「作品のなかで“多様性”を描くということ ― 映像制作の現場から」
登壇者:村瀬健 氏(フジテレビ ドラマ制作部 統括チーフプロデューサー)
蓮行 先生
基調トークセッションでは、『silent』『BOSS』『14才の母』などの話題作を手がけた村瀬健氏が登壇し、「作品のなかで“多様性”を描くということ」について、ご自身の制作経験をもとに語っていただきました。
■作品制作のなかで必然的に “多様性” を描くことになった

村瀬氏が手掛けてきたこれまでの作品では、さまざまなダイバーシティが描かれています。しかし、全ての作品において必ずしも最初から「多様性を描こう」と意識していたわけではないといいます。
たとえば『BOSS』の企画は、「主演の天海祐希さんに刑事もので上司役を演じて欲しい」という着想からスタートし、制作を進めるなかで「ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン」というテーマにぶつかったとのこと。結果として、社会のなかにある多様な価値観や葛藤と向き合うことになったと語られました。
一方で、『silent』の創作プロセスはまったく逆で、最初から「多様性をテーマにした作品をつくろう」「テレビドラマという場所で、自分が形にできないか」との想いから企画をスタートしたそうです。実際に多くのろう者や中途失聴者の方にお会いし、何度もお話を伺いながら、丁寧に作品制作を進めていったといいます。
■「少ないってことは、いるってことだよね」
『silent』に登場する「想くん」は、生まれつきのろう者ではなく、中途失聴者として描かれています。中途失聴者のなかには喋ることができる方も多い一方で、発声への不安や、過去に笑われた経験などから、喋らなくなる方もいることを取材で知ったと村瀬氏は述べました。そうした背景を踏まえ、想を“喋らない”人物として描いたといいます。
劇中では、紬が「しゃべれるのに、なんでしゃべんないの」と問いかけてしまい、互いに心を痛める場面があります。そこで紬が発する「少ないってことは、いるってことだよね」というセリフは、脚本家によって書かれたものでしたが、村瀬氏は「この作品をつくろうとした自分の原点の想いを、言葉にしてくれたと感じた」と語りました。

■ ぼんやりと観ていた人にも届き、繰り返し観るとより深く楽しめる
作品のつくり方について、村瀬氏は会場からの質問に応じるかたちで、「基本的には、ぼんやり観ている人がおもしろく感じてくれることを意識する」と話しました。その上で、「2回も3回も観たくなるドラマをつくるために、技術を凝らしている」と続けました。
『silent』では、過去や現在、登場人物の背景や関係性などを、作品の随所に散りばめています。2度、3度と繰り返し観ることで、「こんな意味もあったのか」と新たな発見があるように意図的に仕掛けられているのです。
蓮行氏は、「無関心層へのリーチ」という観点からこのアプローチに強く共感。「ドラマプロデューサーの感覚に舌を巻いた」と述べました。魅力的な俳優を起用することも“届ける工夫”の一つ。作品づくりの戦略と社会的意義の接点が語られたやりとりとなりました。
第2部:ポスターセッション・ポスターミーティング

第2部では、会員団体や一般参加者によるポスター発表が行われ、多様性・共生・コミュニケーションに関する実践知の共有が図られました。
会場には企業・非営利団体・教育関係者・京都大学の学生など多様な立場の参加者が集い、各ポスターを囲んで活発な意見交換が行われました。

ポスターセッションでは、会員団体の取り組みに加え、公募により集まったさまざまな実践例が紹介されました。セッション中は、発表者と来場者のディスカッションが各地で生まれたほか、ポスターに対してふせんでコメントを寄せ合う様子も見られ、参加者間で互いの経験や工夫を共有しながら対話を深める場となりました。

続くポスターミーティングでは、会員団体から寄せられたポスター(事例紹介や課題提起など)をもとに、3団体ずつご登壇いただき、ミーティングを行いました。蓮行先生および村瀬氏にもご参加いただき、それぞれの取り組みについて活発な意見交換が行われました。
営利と非営利、規模や業種も異なる登壇者同士の間で、「どうしてこのような取り組みをされるようになったのか」や、「私たちも同じような課題意識を持っているが、御社ではどのような方法で解決を試みているのか伺いたい」といった率直な対話が交わされました。
こうした時間は、本シンポジウムの重要なテーマの一つである、「個々の実践を通じて蓄積された分散知を、対話によって集合知へと高めていく」営みそのものだったと考えます。



最後に
本シンポジウムでは、さまざまな分野から「DE&I」をめぐる課題や実践が共有され、参加者それぞれの現場や立場に根ざした対話が交わされました。
参加者からは、「村瀬さんの『DE&Iを最初から意識したのではなく後付け的に意識するようになった』とのお話にとても共感できた。」「社内でDE&I施策を広げていく上での参考になった。」「ポスター発表が、自分の仕事や活動を見直したり、価値を見出すきっかけになった。」などの声が寄せられました。
DE&Iの推進においては、特定の専門家や当事者に任せきるのではなく、あるいは何かひとつのゴールを達成することを目的とするのではなく、「一人ひとりの異なるニーズや事情に合わせて、環境を調整し続けること」が重要です。それは、常に変化し続ける「プロセスとして捉えること」でもあります。そのためには、たくさんの人たちと出会い、対話を重ねることが欠かせません。
本コンソーシアムでは、これからも「多くの人の声が交わる場づくり」を大切にし、さまざまな立場の方々と共に考え、場を育てていけるよう、努めてまいります。引き続き、ご意見をお寄せいただくとともに、当コンソーシアムの企画にご参加いただけましたら幸いです。


■メディア掲載情報
今回のシンポジウムの内容につきましては、以下のメディアにてご紹介いただきました。ぜひあわせてご覧ください。
ゴム報知新聞
https://gomuhouchi.com/tire/68220
神戸新聞
https://www.kobe-np.co.jp/news/economy/202506/0019143168.shtml
ゴムタイムス
https://www.gomutimes.co.jp/?p=204910
■参加企業掲載情報
住友ゴム工業株式会社 トピックス
https://www.srigroup.co.jp/topics/detail/?topicsno=6956